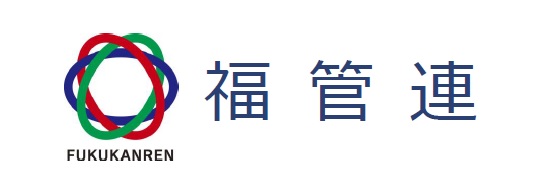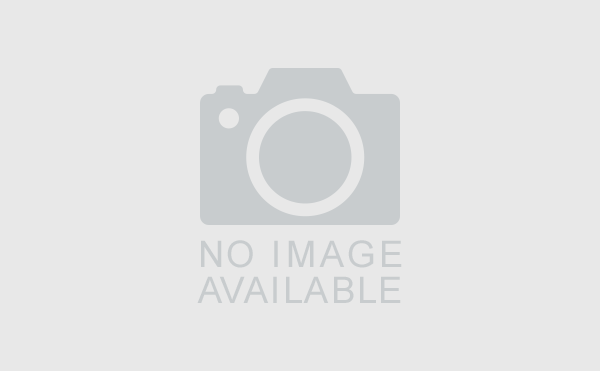区分所有法が20年ぶりに改正
区分所有法が20年ぶりに改正
昭和通り法律事務所 弁護士 安原伸人
令和7年5月23日マンション法が20年ぶりに改正されました。
これにより、管理組合の皆様のマンション管理業務に影響が出てきますので、今回は改正された内容のうち、マンション管理に関して最新情報を提供させていただきます。
総会運営の中でなかなか大変なのは、所有者が不明であったり、国外に居住されている方が区分所有者だったりして、連絡が付かず大変ご苦労をされていると思います。
今回の改正では、この点について条項が変更ないし新設されております。
1 新設:第6条の2第1項(国内管理人制度)
「区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。」
これは、要綱案でも注意書きされているように、規約において国内管理人の選任を義務付けることができることを前提とされています。
したがって、当該改正を念頭においた規約改正を検討すべきでしょう。
2 新設:第38条の2(所在等不明区分所有者の除外制度)
「裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(所在等不明区分所有者)以外の区分所有者(一般区分所有者)又は監理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。」
つまり、所在等不明区分所有者がいる場合、裁判により、当該所在不明区分所有者を決議の分母から除外する制度が創設されました。所在等不明とは、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない(例えば相続人が全員相続放棄、必要な調査を尽くしたが所在が分からない)場合をいいます。
申立ては、当該区分所有者(以下「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者、管理者又は管理組合法人が行うことができます。
所在等不明区分所有者以外の区分所有者も申立てが可能なため、この場合、所在等不明区分所有者の除外決定を受けたときは、管理者又は理事に対し、遅滞なくその旨を通知することとされました。
3 変更:第39条(議事)
「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決する。」
当該変更により、出席者の多数決による決議を可能とする仕組みが創設されました。
適用されるのは、要綱案にも列挙されていた、①普通決議、②共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下同じ。)の決議、③復旧決議、④規約の設定・変更・廃止の決議、⑤管理組合法人の設立・解散の決議、⑥義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議、⑦管理組合法人による区分所有権等の取得の決議(注)本文にいう「出席した区分所有者」には、書面若しくは電磁的方法で、又は代理人によって議決権を行使した区分所有者(区分所有法第39条第2項及び第3項)を含むものとする。
そして、上記①以外の決議については、法律上、原則的な集会の定足数を過半数とした上で、規約でこれを上回る割合を定めることを可能とするものとすることになりました。
例えば、共用部分の変更に関して、17条1項は、「集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する」と変更されました。
4 変更:第35条1項(招集通知)
「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる」
この改正により、集会の招集の通知は、これまで、原則として、会議の目的たる事項だけでよかったのですが、必ず議案の要領を示して、各区分所有者に発しなければならないことになりました。また、除外された所在等不明区分所有者に対しては招集通知さえいらないことになりました。
5 変更:第40条(議決権行使者の指定)
「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない」
改正前において、
専有部分が共有の場合、解釈上、区分所有権が共有の場合全員合意により、議決権行使者を指定するべきとされてきましたが、改正法では、共有者は、各共有持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めることが可能となりました。
6 財産管理制度の創設
第六節として「所有者不明専有部分管理命令」が新設、その節中において、第46条の2が新設されて、所有者不明専有部分管理制度が創設されました。
また、第七節として「管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令」が新設、その節中で第46条の8ないし14までの条項が新設されて、管理不全専有部分管理制度(第46条の8)、管理不全共用部分管理制度(第46条の13)が創設されました。
7 共用部分の変更決議及び復旧決議の多数決要件の緩和
(1)共用部分の変更に関し、一定の要件(危険性要件)で3分の2に緩和されました(新設:17条5項)
(2)復旧決議に関しても3分の2以上の多数決に緩和されました(変更:61条5項)。
8 その他
(1)管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)(新設:5条の2)
「区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。」
(2)他の区分所有者の専有部分の保存請求(変更:第6条2項)
(3)専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)(新設:17条3項、4項)
(4)管理組合法人による区分所有権等の取得(新設:52条の2)
(5)共用部分等に係る請求権の行使の円滑化(変更:26条2項)
なお、今回の改正後のマンション法は、令和8年4月1日から施行されますが、改正法施行の際現に効力を有する旧マンション法の規定による規約で定められた事項で新マンション法に抵触するものは、施行日からその効力を失うとされており、改正マンション法施行以降に、改正法に抵触する規約は無効となります。
ただし、改正法の施行日前に旧区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、旧法に従うものとされます。
以上のように、改正は多岐に渡っており、標準管理規約の改正も待たれるところですが、できるところから、今回の改正点を踏まえて規約改正を検討されることをお勧め致します。